|
|
|||||
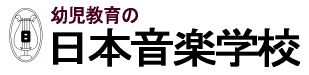 |
「平成18年度 入学式の報告」 |
平成18年度 入学式  |
4月5日(木)に平成18年度入学式が挙行されました。小林校長をはじめ教員はもちろん、来賓の方々、同窓会の方々、学校関係者、そしてこれからの生活を共にする先輩たちが新入生をあたたかく迎え、日音の新しい1年がスタートしました。 以下に、2年生による「新入生を迎えることば」と新入生による「新入生誓いのことば」を掲載いたします。 この4月から日音ではホームルームを1・2年生合同としました。先輩と後輩の関係を大事にし、日音の校風を先輩から後輩へと引き継ぐ環境を積極的に設けたいと思ったからです。日音は学生同士が切磋琢磨し、成長しあう場所です。「歓迎のことば」と「誓いのことば」はそれを象徴しています。 We are changing!Never Stop! 日本音楽学校は、最高の教育を目指して歩み続けます。 |
「校長式辞」 日本音楽学校長 小林 志郎  |
新入生の皆さん、入学おめでとう。また保護者並びにご家族の皆さん、知人友人の皆さんにもお祝いの言葉を申し上げます。 本日は東京農業大学教授、元衆議院議員・栗本慎一郎先生をはじめとして来賓の方々をお迎えし、入学式を挙行することになりました。大変、嬉しく、栄誉なことです。心からお礼申し上げます。 今日は三つのことをお話します。 昨年の入学式でこうお話しました。 学生のためになると分かったことは、すぐにやってみる。これが日本音楽学校の教育哲学であると。 そういう姿勢でこれまで五年間にたくさんの教育リフォームを進めてきました。 ミニュツ・ペーパーの導入が最初でした。ミニュツ・ペーパーとはせいぜい1分間ぐらいの短時間で仕上げる点検ペーパーという意味だと思ってください。何を書くのかというと、今九〇分かけて行われた授業について、短い時間で答えていただくのです。 ちなみに、予習をしたか、授業の速さは、内容を理解できたか、教師の話し方は明瞭だったか、教師は重要な点を明確にしたか、質問したり発言をうながしたりしたか、という設問に五段階のエバリュエイションをしていただくのです。みなさんは四月の授業から早速体験します。 私たちのリフォームは、このほかに、皆さんが授業を採点する授業評価、AO入試、授業の助手をするTA制度、長期間かけて実習を経験するセメスター実習、禁煙という新しい文化の導入、授業の出欠を毎月学生にアナウンスする教務サービス、保育研究発表会の改革など数え切れないリフォームが行われてきました。 ほとんどのリフォームは予想した成果を上げることができました。それはとりもなおさず学生諸君の善意にあふれた挑戦があったからです。学校という教育システムは学生と教員と職員によって動かされています。 ところがこれまで日本の教育は、教職員が学生を管理する形態で進められてきました。あるときまでそれでよかったのです。学生が主役であるという考えが導入されたのはここ二十年ぐらいでしょうか。 学生諸君の理解、協力がなければいかなるリフォームも成功しません。ひとえに皆さんの先輩たちの働きによって本校の教育改革は達成できたのです。教職員の努力でリフォーミングができたのですが、でもやはり主役は学生です。 禁煙への取り組みは、決して生易しい活動ではありませんでした。三年の間に、何人もの学生に停学を申し渡さざるを得ませんでした。今式に参列している二年生がリーダーシップを発揮してくれ、四年目にして禁煙ということばが日本音楽学校のキャンパスから自然消滅することを期待しています。 二つ目に私たちの教育姿勢についてお話しましょう。 教育の機会はできる限り多くの青年に与えなければならない。若者を排除する教育姿勢はいけない。やる気がある限り、教育を受ける機会を与えよう。これが私たちの教育姿勢です。 私は教員の方々に、試験は何のためにやるのか考えてほしいと話しています。 前向きな試験のあり方として、理解してほしいと思う理論を理解する助けとなる試験、マスターして欲しいと期待する技能を習得する助けとなる試験、その上で学力や学習成果を判断できる試験を追及したいと思っています。 よく予想した試験問題が出た出ないと学生時代に喜んだり、悲しんだりした記憶があります。しかし根本を考えてみると、何が大切か教師が明らかにしなかったから起こる現象であり、教育は予想能力を高めるためにやっているわけではありません。 大事なら、大事だとはっきりさせる。学生みんなが大事だと信じ、予習する。だからあたりとかはずれとかがない。こういう試験があってもよいと考えます。 カリフォルニア大学ロスアンジェルス校UCLAで、大学の先生に講義の仕方を教える教員用教科書 ABC’s of Teaching with Excellence という本が出版されています。授業のやり方や試験のやり方の事例をまとめ、解説した中で、学生・教員ともに高い評価を与えた試験形式を紹介しています。どういう試験だと思いますか。それは試験問題を学生が作成する形式です。出題の内容・意図・重要度を教員と学生で検討し、双方の意見をもとに試験問題を決めるのです。 此の試験を独創的で、かつおもしろくするため、ある人がさらに工夫を加えました。その改良点とは、教員が模範解答を作成し、試験の三日前に学生に配布するようにしました。その結果、この試験スタイルは大評判になりました。 参考書やノートを持ち込んでもよい試験であり、何を復習し、準備したらよいかわかる「試験を使った学習」であり、さらに自分の考えを書き加えることで点数が加算される試験であるのです。 日本音楽学校でもユニークな試験があっていい、むしろあって欲しいと願っています。 こんなお話をしたのは、学校は今社会から開かれた学校へと転換することを求められているからです。最初に教育そのものがオープンになるよう求められました。その結果、学生による授業評価が唱えられました。本校は他の養成校や短大に先駆けて四年前に学生による授業評価に挑戦しました。これは画期的な教育リフォームでした。 今、私たちは教育をオープンにし、内外からの評価を受けるため、教育という仕事をガラス張りにする工夫をしています。 学生や同僚の評価に耳を傾け、潔く、見栄やプライドを捨てていい授業を作ろうとする姿勢を持ち続けようとしています。 今年、私たちはまた少し変化するでしょう。ご期待ください。 三つ目は 昨日までは結構うぬぼれていましたが、教育に対する熱意について私が心を入れ替えた話です。 授業評価、シラバス、教育サービスということばに意外に反発しているのがイギリスの教員です。教員評価には決していい顔をしません。しかし昨日、この七月末に美術セラピーの授業をワークショップ形式でやってくれるDR. Susan Hoganから書類の入った郵便物が届きました。日本では四月に新学期が始まると聞いているので日本音楽学校の一年生のオリエンテーションに間に合うようお送りしますと書いてきました。 彼女、曰く。セレモニーやオリエンテーションで是非伝えてください。私が日音の学生とセラピーの体験授業を通して触れ合うことにわくわくしていると。 書類は全部で3種類ありました。「セラピーの体験的学習とは」という「授業のチラシ」A4で4枚と、授業の詳しいやり方と展開を書いた講義ノート、そして資料集でした。 Dr. Susan Hoganは日音での授業の段取りを昨年夏から考え続けて、新学期のスタートにあわせて送ってきてくれたわけです。私たちもシラバスを作成し、教材研究・開発に熱心ですが、今年の七月に集中講義を担当してくれる英国人の教師が私たち以上に準備をしていることを知って愕然としました。 昨年、彼女にあったとき、英国では評価だシラバスだと面倒くさい要求が多いのですが、日本でも同じですか、とたずねられました。日本は英国の教育の真似をし、英国は日本の教育のまねをしていますから、やり方は違ってもやっていることは同じですよ、と答えました。じゃ、文句を言っても仕方ないですね、いい授業をするよう努力します、と言いました。その本人がこんなに用意周到な準備をしていたとは驚きです。きっとDr. Hoganはいい授業をしてくれるものと確信しています。 私たちの使命は、社会が求めている教育、学生が求めている教育、そして私たちが皆さんのためになると信じている教育をサービスすることです。皆さんが一日も早く本校にお慣れになって、やるべきことはやり、その上で自分の得意分野を開拓するために努力してくださることを願ってやみません。 本年度の入学式は二年生がこのように皆さんをお迎えする位置にいます。私には彼らが心地よい緊張感を漂わせているように見えます。心なしか頼りがいのある顔つきをしています。おそらく新入生が順調にキャンパス・ライフをスタートできるよう支援・指導をしたいと考えているからに違いありません。 二年生諸君、よろしくお願いします。 最後にもう一度、一年生の諸君にお祝いを申し上げます。入学おめでとう。以上で私の挨拶といたします。 |
「新入生を 迎えることば」 在校生代表 保育士・幼稚園教員コース2年 藤井 知子  |
春の心地よい風が私達を包み、希望でつぼみを膨らませた花々が楽しげに咲き誇るこの頃となりました。この良き日にご入学された皆様、本日は誠におめでとうございます。今日という日を皆様は様々な思いで迎えられたことでしょう。 思い起こせば一年前、私も緊張しながら入学式に参列していたことが思い出されます。私は、大学を卒業後、しばらく就職した後に本校に入学いたしましたので、久々に講義を受けることや学生間の年齢差に不安を感じていました。 しかし、この一年間、大変充実した学園生活を送ることができました。学校での学習は保育に関連する政治経済、文化、芸術、文学についての私の関心を知らないうちに高めてくれました。 その中でも、12月に行われた保育研究発表会は大変実り多いものでした。保育研究発表会ではクラス全員が一丸となって作品を作り上げ、大きな感動と達成感がありました。話し合いから本番を迎えるまで、楽しさや期待だけでなく、意見の対立や責任が重くのしかかっていたり、力を十分に発揮できなかったり、と様々な場面がありました。しかし、気持ちをお互いに伝え合い、分かち合うことにより一致団結し、精一杯やり遂げることができました。 また、実習では子どもと深く関わる事ができ、大変充実した日々を送ることができました。毎日、日誌や指導案を書くなど大変なことも多くありましたが、子どもの笑顔はどんなに疲れていても頑張ろうという気持ちにさせてくれました。子どもたちの表現力や発想の豊かさに触れこの経験を通して改めて保育者として働きたいという気持ちが強くなりました。 今、私たちを取り囲む環境は動いています。子どもたちと打ち解けて、一緒に遊び、手遊び、ゲーム、お話がベテランの先生のように出来ることはもちろん大切です。 さらに、2年間で多くの基礎技術、知識、応用力、想像力そして、何よりも子どもたちに対する深い愛情とコミュニケーション・スキルを持つことを私たちのテーマとして学習することも必須です。その上で、保育の現状、私たちに何が求められているか、保育の将来についても心していく必要があります。 日本音楽学校の卒業生、つまり私たちの先輩の方々は保育の世界で優れた活躍をなさっていると伺っています。私が行った実習先でも指導して下さった先生が本校の卒業生でした。 先輩の方々が築いて下さった日本音楽学校の幼児教育の歴史の上に新しい歴史を書き込んでいくのが私たちの使命であると今、私は考えます。 本校の授業は楽しく、厳しく、やるべきことが間断なく流れてきます。トータルとして学ぶ力、判断する力、そして、得意分野を作る学習を尊重する本校の教育を私は高く評価しています。入学してよかった、ここで学ぶことが出来て幸せであると思っています。 新入生の皆さん、日本音楽学校の学生であるという誇りを胸に、私達と共に有意義な学生生活をスタートさせましょう。これからの二年間は楽しいことだけでなく、苦しいときもあると思いますが、保育者となって現場で働く上で大きな財産となると思えば乗り越えることが出来ると思います。簡単ではございますが、これを歓迎のご挨拶とさせて頂きます。 |
「新入生 誓いのことば」 新入生代表 保育士コース 櫻井 彩加   |
あたたかな春の陽射しに照らされ、かわいらしいたくさんの花々が彩りを加える季節となりました。 みなさんは、学園の横にある櫻の木に気付かれたでしょうか? 今まさに咲き誇る姿はまるで私たちを歓迎してくれているかのように見えます。このような良き日に、盛大な入学式を開いてくださり、ありがとうございます。 今日こうして新入生として新たな第一歩を踏み出すことができ大変嬉しく思います。 さて、私たちが保育者を目指し日音を選んだことにはさまざまな考えや理由があったと思います。私にも同じような想いがありました。 私事の話になりますが、私は幼少の頃からずっと幼稚園教諭になりたいと強く思っていました。意思が揺らぐことなく夢を持ち続けていました。 自分の将来について真剣に考え、短大で勉学に励み夢の実現に専念しました。その一方で、保育士にも興味を持ち保育所でのボランティア活動やアルバイトを経験しました。 卒業後、幼稚園に勤めましたが、退職を機にもう一度保育士として頑張りたいと新たな挑戦を思い立ったのです。 日音には、昨年の秋初めて訪れました。本学を卒業した友人から日音の話を聞き、ぜひ行ってみたいという思いが生まれ、自分なりにリサーチした後に、学校見学をしました。 その後、入学説明会にも参加しより深く日音を体験することができました。その際の在学生の方のお話や、熱意溢れる校長先生のスピーチがとても印象的でした。 また授業体験では、先生と学生がお互いに言葉や心のキャッチボールをできるようなあたたかい雰囲気を感じられました。 このような教育環境の中で、本当の意味での信頼関係が育まれ、授業展開がなされていくことの大切さを実感しました。 また、日音には他校には見られない独自のカリキュラムがあることを知りました。 補習授業制度やジョブ・ハンティングがそれです。 補習と聞くと一見マイナスなイメージに捉えられがちですが、全くそのようなものではなく、さらに自身を高めるために積極的に取り入れられているものです。 昨今の就職状況は回復傾向にありますが、それでも依然困難である事には変わりありません。しかし、日音では先生と学生が強く支え合い励まし合いながら歩んでいく環境作りに力を入れているので、最後まで安心して就職へと辿り着くことができると思います。 また、本年度からは基礎教養力を養うことを目的として、芸術セラピーという講座が開設されます。保育者として、専門分野の知識を深めることは大切です。しかし、ただそれだけではまだ十分ではないと思います。 保育者に対するニーズも多様化する現代においては、プラス・アルファの部分も必要になってくると思います。一般教養として身につける事柄が新しい自分づくりにも繋がると思います。 数年後、社会に出た時きっと役に立ち自分の得意分野として胸を張れるはずです。 幾つかお話させていただきましたが、このような素晴らしい環境の中で生活できると思うと、とてもわくわくします。 しかし、期待に溢れる一方で多少の不安もあります。楽しいだけでなく実習等においては辛さや厳しさを味わうこともあると思います。そんな時には、先輩方の頑張る姿を見て私たちも前向きな気持ちで頑張ります。 ご来賓の諸先生方、日本音楽学校の理事長先生、校長先生をはじめとして全ての教職員の方々、同窓会の皆さん、そして何よりも身近な2年生の皆さん、今日、お会いできた幸せを胸に日々努力することを誓います。どうぞご指導のほどよろしくお願い致します。 簡単ではありますが、誓いのことばとさせていただきます。 |
日本音楽学校 〒142-0042 東京都品川区豊町2-16-12 電話:03-3786-1711 / FAX:03-3786-1717 / E-Mail:info@nichion.ac.jp (C)学校法人 三浦学園 |